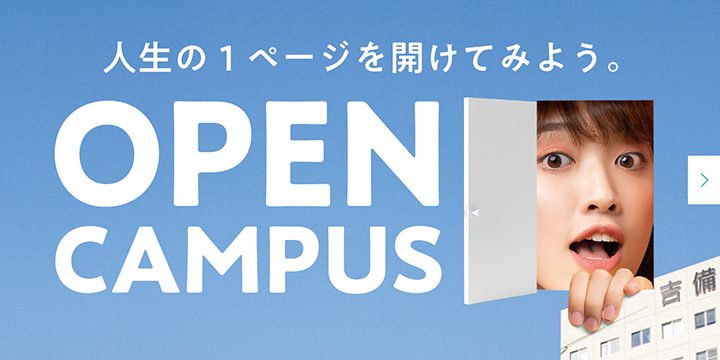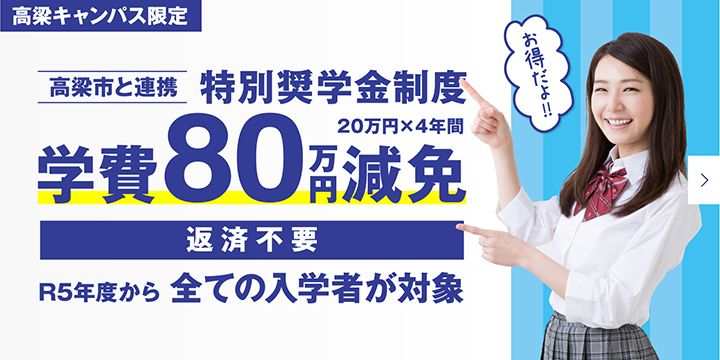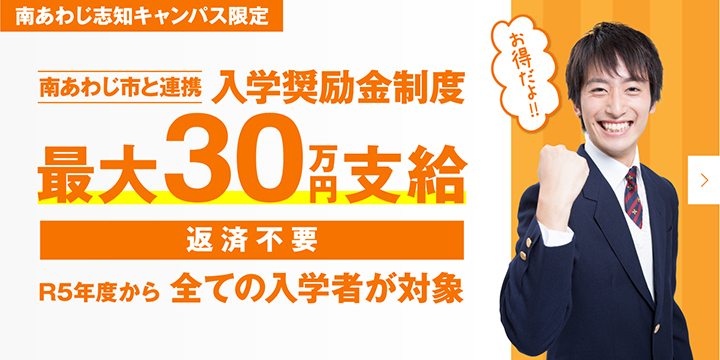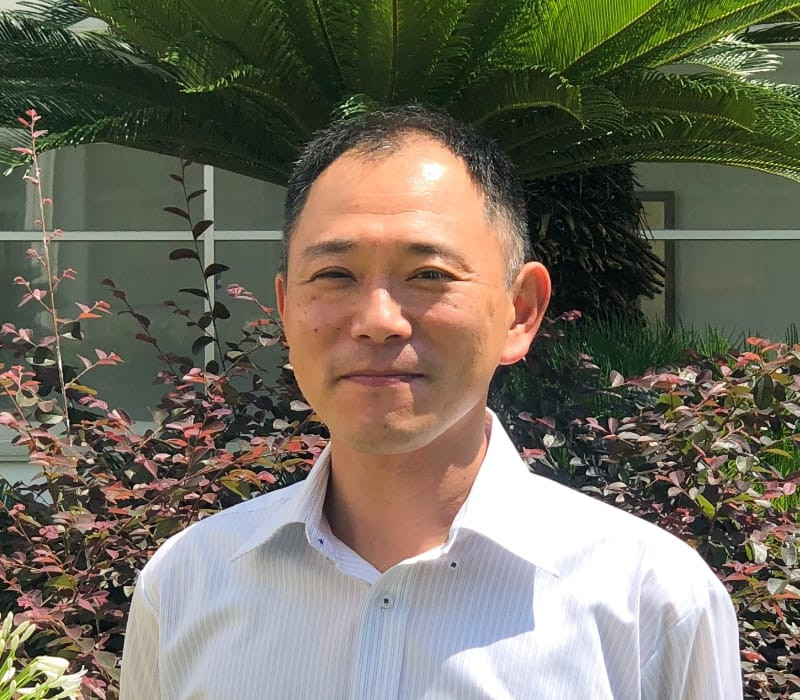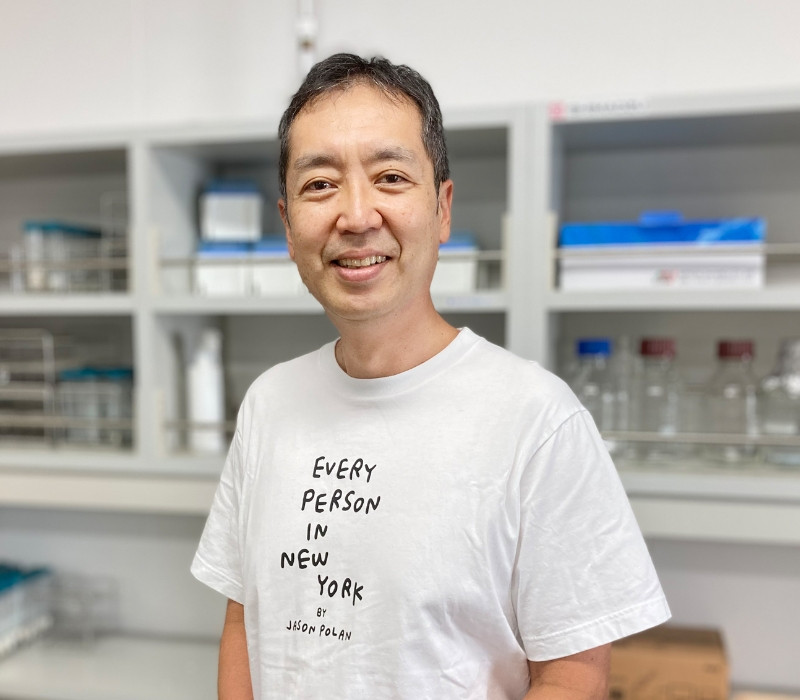大学院
通学制地域創成農学研究科博士(前期)課程・博士(後期)課程
教育目標
地域創成農学専攻 博士(前期)課程
農業生産、⾷品加⼯、農業経営全般にわたる専門的知識や技術、地域社会や国際社会における農業の状況や位置づけ に対する理解を⾝につけ、習得した⾼度な専門分野の知識及び技術を活かして、農業をはじめとする地域産業の振興へ の貢献など、地域の活性化に寄与できる専門的職業⼈の育成を目指す。さらに、⾼⽔準の英語能⼒を⾝につけ、国際社 会で指導的役割を果たすことのできる⼈材の養成、及び、より⾼度な研究活動に取り組む研究者(博士(後期)課程進 学者)の養成も視野に入れている。
博士(後期)課程
農業生産、食品加工、地域経済社会に関わる学術分野及びそれら分野の学際領域に関して深い学識を持ったうえで、世界トップレベルの先端研究を自立して行える能力と高い倫理性を有し、国際的に活躍する高度学術研究者の養成を主たる目標とする。
人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的
- 博士(前期)課程
- 農業生産、食品加工、農業経営全般にわたる知識と技術を幅広く身につけることを基礎として、地域社会や国際社会における農業の状況や位置づけを的確に捉え、専門分野の探求によって培った知識や技術を通して、地域社会の活性化に寄与できる高度な専門的職業人の育成を目的とする。
- 博士(後期)課程
- 農業生産、食品加工、農業経営・流通の全般にわたる知識と技術を幅広く身につけたうえで、地域社会や国際社会における農業の状況や位置づけを的確に捉える能力や、専門分野における高度な知識と技術を身につけた、研究者あるいは専門技術者の養成を目的とする。
研究科の3つのポリシー(学位授与方針、教育課程の編成・実施方針および学生の受入れ方針)について
概要
地域創成農学研究科 地域創成農学専攻
指導教員・研究分野
博士(前期)課程
レタスビッグベイン病の防除法の開発/イネにおける赤かび病の発生状況とカビ毒汚染の実態調査/キノコ廃菌床を用いた、地域特産農作物の病害防除
教授村上 二朗むらかみ じろう
- 主な担当授業科目:植物病理学特論、植物保護学演習
- 詳細を見る
生態系サービスの評価に関する研究/生物多様性の保全に関する意識分析/獣害防除を意図した里山・農地管理システムの構築
教授森野 真理もりの まり
- 主な担当授業科目:植物保護学特論、植物保護学演習
- 詳細を見る
微生物発酵を用いた淡路島特産農産物の高付加価値化/淡路島特有の酪農加工品の開発/食品中の高機能性化合物の分析
講師林 将也はやし まさや
- 主な担当授業科目:機能性分析学特論、食品機能開発化学演習
- 詳細を見る
博士(後期)課程
アラブ・イスラーム社会の出生規範/小地域社会を対象とした将来人口推計/南あわじ市の第一次産業従事者の生業戦略
教授末吉 秀二すえよし しゅうじ
- 主な担当授業科目:地域経済社会学フロントライン
- 詳細を見る
レタスビッグベイン病の防除法の開発/イネにおける赤かび病の発生状況とカビ毒汚染の実態調査/キノコ廃菌床を用いた、地域特産農作物の病害防除
教授村上 二朗むらかみ じろう
- 主な担当授業科目:植物保護管理学フロントライン
- 詳細を見る
生態系サービスの評価に関する研究/生物多様性の保全に関する意識分析/獣害防除を意図した里山・農地管理システムの構築
教授森野 真理もりの まり
- 主な担当授業科目:植物保護管理学フロントライン
- 詳細を見る
閉鎖型植物工場に適応する農作物の研究/開放型植物工場に適応するトマトの育種/植物工場を利用して農作物の栽培に関する研究
講師許 冲きょ ちゅう
- 主な担当授業科目:栽培・育種学分野学位論文研究
- 詳細を見る
研究対象とする中心的な学問分野について
本研究科において組織として研究対象とする中心的な学問分野は、「栽培・育種学分野」、「植物保護学分野」、「⾷品機能開発化 学分野」及び「農業経済学分野」の4分野とし、関連分野に関する基礎的素養の涵養を目指す科目群として、「専攻共通科目」 を設けている。 科目区分の上で専門科目の柱となる4分野のうち、「栽培・育種学分野」、「植物保護学分野」、「⾷品機能開発化学分野」の3分 野においては、「特論」、「演習」、「専攻実験」を組み合わせ、理論と実践による相乗効果の高い構成としている。また、「農業経 済学分野」は、「特論」と「研究演習」を有機的に結びつけることによって教育効果の向上を図る。
栽培・育種学分野
栽培・育種学分野では、農業生産、⾷品加⼯、農業経営・流通に関する専門知識を有し、農業生産上重要な栽培・育種学に関し て特に高度な専門知識と技術、さらには研究能⼒を有する学生を養成する。この目的に沿って、栽培・育種学の全般及びトピッ クスを学ぶ「栽培・育種学特論」、遺伝⼦分析や量的形質遺伝⼦座解析、ゲノムワイドアソシエーション解析、RNA⼲渉、遺伝 ⼦組換え、ゲノム編集、ゲノミックセレクションなど、植物のゲノム解析に必要な諸技術、⼿法の理論を学ぶ「植物ゲノム解析 学特論」を設ける。また、栽培学・育種学における研究の現状を理解させるとともに、ディスカッション及びプレゼンテーショ ン能⼒を育むための「栽培・育種学演習」、さらに栽培学と育種学研究に関する専門技術を修得するための「栽培・育種学専攻実 験」を提供する。
植物保護学分野
地域における農作物を病虫害や獣害等から守り⾷料生産の持続性を確保する上で、植物保護学が重要である。そこで、植物保 護の基礎と応⽤に関して「植物保護学特論」と「植物病理学特論」を設ける。「植物保護学特論」では薬剤耐性菌の発達など農 薬を主体とした防除に伴う問題点、それらを克服するための病害抵抗性品種の育成や病害抵抗性誘導剤の開発・利⽤、獣害の実 態と対策などの事例を紹介して作物保護に関する先端的な情報の習得を目指す。また、これらの問題に関して「植物保護学演習」 や「植物保護学専攻実験」で取り組み、独創的な研究の成果を地域のみならず国内外に発信して安定的な⾷料生産に活かして⾏ く。
食品機能開発化学分野
⾷物はヒト体内の様々な受容体や酵素タンパク質に作⽤して生命機能を調節している。「⾷品栄養機能学特論」では、ポリフェ ノールやテルペノイドなどの植物二次代謝産物が持つ健康増進機能についての知識習得を目指し、⾷品機能性成分を検出・定量 するための極性を利⽤した選択的に抽出する科学的⼿法を学ぶために「機能性分析学特論」を設ける。また、⾷品成分機能の有 効性を理解する能⼒を「⾷品機能開発化学演習」で養い、講義・演習で得た知識を応⽤し機能性成分を含みかつ美味しい地域特 産の農産品の開発を「⾷品機能開発学専攻実験」で取り組む。
農業経済学分野
現代日本農業が抱える構造的問題(例えば、担い⼿不⾜や経営規模の零細性、⼟地の分散性など)を把握し、経済学的にその 要因や動向を分析するために「農業経済学特論」を設ける。また、経済発展のメカニズムの中での農業・農村問題の位置づけや 国⺠経済の発展に伴う問題の変容を学ぶために「開発経済学特論」を設けている。さらに、論⽂作成に必要な学術スキル(例え ば、適切な課題設定の仕方、計量分析や現地調査の方法等)を、「農業経済学研究演習Ⅰ」及び「農業経済学研究演習Ⅱ」の履 修を通じて学び、修士論⽂の作成に向けて指導していく。
専攻共通科目
この分野は、専門科目で⾝につけた知識や技術を通して地域創成を始めとする社会貢献に活かすための基礎的要素を養う分野 と位置づけ、「地域創成農学特論」、「地域創成農学特別講義Ⅰ」、「地域創成農学特別講義Ⅱ」、「地域創成農学特別講義Ⅲ」、「地 域創成農学特別講義Ⅳ」、「地域環境学特論」、「国際農業学特論」、「農業経営学特論」を置く。 この分野は、「地域社会や国際社会における農業の状況や位置づけを的確に捉え、専門分野の探求によって培った知識や技術 を通して、地域社会の活性化に寄与」していくための問題意識や課題の認識、課題解決への思考⼒、専門研究の応⽤⼒等を養う ための科目として位置づけている。
さらに、将来の国際的な活躍や博士課程への進学を視野に⼊れ、ビジネス英語科目を設けている。
カリキュラム
地域創成農学専攻 博士(前期)課程
わが国においては「地方創生」が大きなテーマとなっており、多くの関心が寄せられている。その課題解決のためには、今日、 衰退に直面している日本の多くの地域社会を再生し、新たな形で創成していくことが求められている。したがって、農村地域の 創成を担う優秀な人材の育成は、今日の我が国の高等教育機関に課せられた喫緊の課題の一つであると考えている。 そこで、本専攻は、農業生産、⾷品加⼯、農業経営全般にわたる知識と技術を幅広く⾝につけることを基礎として、地域社会 や国際社会における農業の状況や位置づけを的確に捉え、専門分野の探求によって培った知識や技術を通して、地域社会の活性 化に寄与できる高度な専門的職業人の育成を目的としている。このため本研究科の教育課程は、「栽培・育種学分野」、「植物保護 学分野」、「⾷品機能開発化学分野」及び「農業経済学分野」の4分野を置くこととし、関連分野に関する基礎的素養の涵養を目 指す科目群として、「専攻共通科目」を設ける。
| 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | |||
| 地域創成農学特論 | 1春 | 2 | ||
| 地域創成農学特別講義Ⅰ | 2秋 | 1 | ||
| 地域創成農学特別講義Ⅱ | 2秋 | 1 | ||
| 地域創成農学特別講義Ⅲ | 2秋 | 1 | ||
| 地域創成農学特別講義Ⅳ | 2秋 | 1 | ||
| 地域環境学特論 | 1秋 | 2 | ||
| 国際農業学特論 | 1秋 | 2 | ||
| 農業経営学特論 | 1秋 | 2 | ||
| アグリビジネス英語Ⅰ | 1春 | 1 | ||
| アグリビジネス英語Ⅱ | 1秋 | 1 | ||
| アグリビジネス英語Ⅲ | 2春 | 1 | ||
| アグリビジネス英語Ⅳ | 2秋 | 1 | ||
| 小計(12科目) | ― | 8 | 8 | - |
| 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | |||
| 栽培・育種学特論 | 1春 | 2 | ||
| 植物ゲノム解析学特論 | 2春 | 2 | ||
| 栽培・育種学演習 | 1~2通 | 8 | ||
| 栽培・育種学専攻実験 | 1~2通 | 8 | ||
| 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | |||
| 植物保護学特論 | 1春 | 2 | ||
| 植物病理学特論 | 2春 | 2 | ||
| 植物保護学演習 | 1~2通 | 8 | ||
| 植物保護学専攻実験 | 1~2通 | 8 | ||
| 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | |||
| 食品栄養機能学特論 | 1春 | 2 | ||
| 機能性分析学特論 | 2春 | 2 | ||
| 食品機能開発化学演習 | 1~2通 | 8 | ||
| 食品機能開発化学専攻実験 | 1~2通 | 8 | ||
| 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | |||
| 農業経済学特論 | 1春 | 2 | ||
| 開発経済学特論 | 2春 | 2 | ||
| 農業経済学研究演習Ⅰ | 1~2通 | 8 | ||
| 農業経済学研究演習Ⅱ | 1~2通 | 8 | ||
| 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | |||
| (研究指導) | 1~2通 | 0 | ||
- ※修了要件必修科目8単位、及び、所属分野の4科目20単位を含む合計32単位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査及び最終試験に合格することとする。
地域創成農学専攻 博士(後期)課程
地域創成農学研究科博⼠(後期)課程は、農業⽣産、⾷品加⼯、地域経済社会に関わる学術分野及びそれら分野の学際領域に 関して深い学識を持ったうえで、世界トップレベルの先端研究を⾃⽴して⾏える能⼒と⾼い倫理性を有し、国際的に活躍する⾼ 度学術研究者の養成を主たる目標とする。すなわち、博⼠(前期)課程では、「農業⽣産、⾷品加⼯、農業経済全般にわたる知 識と技術を幅広く⾝につけることを基礎として、地域社会や国際社会における農業の状況や位置づけを的確に捉え、専門分野の 探求によって培った知識や技術を通して、地域社会の活性化に寄与できる⾼度な専門職業⼈の養成を目的とする」を目標として おり、学術研究者ではなく、専門知識と技術を活かした特定の職業に従事する⾼度専門技術者の養成を目標としている。これに 対して、博⼠(後期)課程では、博⼠(前期)課程で培った専門知識と技術を⼀層⾼度化させ、学術研究において世界トップレ ベルの先端研究を⾃⽴して⾏える能⼒を有し、⾼い倫理性と豊かな国際性を併せ持った学術研究者の養成を目的とする。
このため本研究科博⼠(後期)課程の教育課程における科目区分は、「栽培・育種学分野」、「植物保護管理学分野」、「⾷品機能 開発化学分野」及び「地域経済社会学分野」の4分野別とし、さらに、関連分野に関する基礎的素養の涵養を目指す科目群とし て、「専攻共通科目」1科目を設けている。
これら科目から、「必修の専攻共通科目(地域創成農学フロントライン)」2単位、所属分野の3科目14単位を含む合計16 単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえで、博⼠論⽂の審査及び最終試験に合格した者に対して、博⼠(農学) の学位を授与する。
| 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | |||
| 地域創成農学フロントライン | 1前 | 2 | ||
| 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | |||
| 栽培・育種学フロントライン | 1後 | 2 | ||
| 栽培・育種学演習 | 1~3通 | 12 | ||
| (栽培・育種学分野学位論文研究) | 1~3通 | 0 | ||
| 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 自由 | |||
| 植物保護管理学フロントライン | 1後 | 2 | |||
| 植物保護管理学演習 | 1~3通 | 12 | |||
| (植物保護管理学分野学位論文研究) | 1~3通 | 0 | |||
| 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 自由 | |||
| 食品機能開発化学フロントライン | 1後 | 2 | |||
| 食品機能開発化学演習 | 1~3通 | 12 | |||
| (食品機能開発化学分野学位論文研究) | 1~3通 | 0 | |||
| 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 自由 | |||
| 地域経済社会学フロントライン | 1後 | 2 | |||
| 地域経済社会学演習 | 1~3通 | 12 | |||
| (地域経済社会学分野学位論文研究) | 1~3通 | 0 | |||
- ※修了要件必修科目2単位及び所属分野の3科目14単位を含む合計16単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格すること。
修了後の進路
修了後の進路として、以下に示す、農業の一次生産、食品化学・加工、農業経営・食品流通分野等における活躍を期待しています。
| 栽培・育種学分野 植物保護学分野 |
農業経営、国及び地方自治体の公務員、青年海外協力隊、農業協同組合、種苗会社、造園会社、農薬会社、商社、食品会社、スーパーマーケット等の食品流通会社、外食産業会社、農業生産法人等を想定しています。さらに、農業技術に不可欠な栽培、育種の素養に加えて病虫害などの防除に関する科目を修得することにより、将来、技術士(農業部門・植物保護)を目指すことも可能です。 |
|---|---|
| 食品機能開発化学分野 | 食素材前処理産業、食品製造・加工業、食品卸・小売業、レストラン等の飲食業、農業協同組合等への就職を想定しています。 |
| 農業経済学分野 | 国及び地方自治体の農林水産関係の公務員、農業協同組合、食品加工会社、スーパーマーケット等の食品流通企業、外食産業、園芸店、食や農に関するNPO、農業生産法人、農業経営等がある。さらに近年、製造業や流通業等の農業参入が増加傾向にあり、新たな就職先として期待しています。 |
大学院入試
大学院の入試情報については、こちらをご覧下さい。