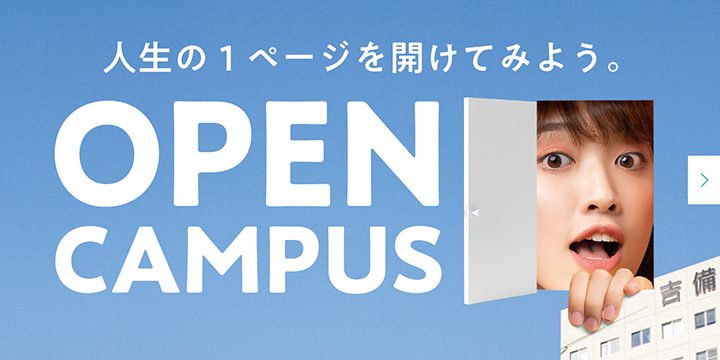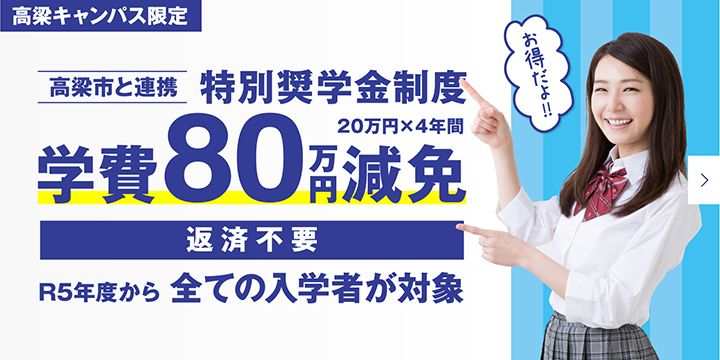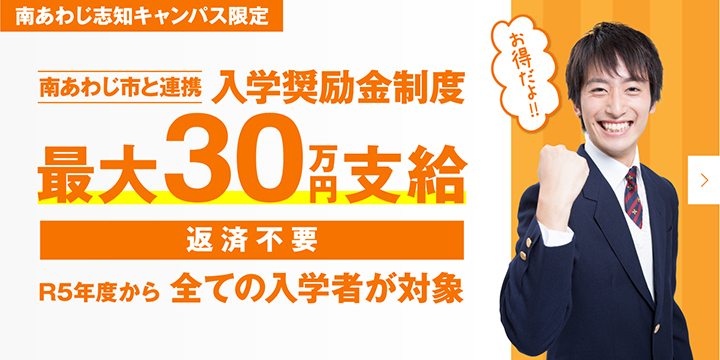キビコクNEWS
【経営社会学科】学生会館(KIUB)カフェスペースで第70回「フリーコーヒー」を実施―学部を越えた学びの協働―【大西ゼミ】
- 経営社会学科
▲70回目のフリーコーヒー準備に取り掛かり、学生に支持をする大西先生(中央)
▲大西ゼミのメンバー(左から①アロカさん(4年)、②二シャーダニさん(3年)、
③シャーニカさん(3年)、④スレーシさん(4年)、⑤トゥエンさん(3年)
吉備国際大学では、「地(知)の拠点」として地域と連携した実践型教育を推進しています。学生は地域の現場に出向き、行政・企業・市民との協働を通して、課題発見力・構想力・協働的実践力を育んでいます。こうした活動は、教室での理論学習と地域での実践を往還する「越境学習」として位置づけられ、キャリア形成や社会人基礎力の育成にも直結しています。
10月17日(金)、高梁キャンパス学生会館(KIUB)2階のカフェスペースにて、大西ゼミ(経営社会学科・大西正泰 講師)が中心となり、第70回目となる「フリーコーヒー」を開催しました。今回は心理学部心理学科の学生3名が協働し、学部を越えたコラボレーションとして実施されました。
今回のフリーコーヒーに参画してくれたメンバーは、大西ゼミでは、G.WEERASINGHE ALOKA CHATHURANGANEE(アロカ)さん、MADDUMAGE DON SURESH MADURANGA(スレーシ)さん、R.V.P.D.MADHUMADHAWA NISHADANI(二シャーダニ)さん、SAHIET GNI SHEHANI SHANIKA(シャーニカ)さん、NGUYEN THANH TUYEN(トゥエン)さん、心理学部心理学科から小井隆之介さん、鮎川千穂さん、吉田晴世さんの3名が参画してくれました。
当日は、ロブスタ種の力強い苦味とカフェインを特徴とするベトナムコーヒーに加え、流通量が少ないスリランカ産コーヒー(通称セイロンコーヒー)を用意。さらに、今年大学でたくさん実をつけた梅がもったいないことから企業とコラボして商品化された「梅クラフトコーラ」も提供し、来場者に好評を得ました。
学生たちは、70回の積み重ねで培ったチームワークと段取りの良さを発揮し、和やかな雰囲気の中で運営にあたりました。
■大学教育における「フリーコーヒー」の意義
フリーコーヒーの取り組みは、単なる「無料の飲み物提供」ではなく、教育的な観点から次の三つの意義を持っています。
❶学びの環境づくり
学生や教職員がリラックスして対話できる場を設けることで、心理的安全性(psychological safety)が高まり、学びやすい雰囲気をつくり出します。教室外の「第三の学習空間」として、越境学習や実践共同体の形成にもつながります。
❷人間関係と理解の促進
フリーコーヒーを介した交流は、学生・教職員・留学生間の相互理解を促す「媒介的装置(mediating device)」として機能します。多様な人が集うことで、共感や協働の学びが生まれます。
❸地域とのつながり
今回は学内実施でしたが、地域で行う場合には、大学が地域連携・地方創生の拠点として機能します。学生が運営に関わることで、地域住民や卒業生も参加できる「開かれた大学」の実現につながります。
また、今回参加した心理学科の学生3名は教育職を志望しています。フリーコーヒーのようなオープンスペースで多様な人と関わる経験は、将来、教育現場で求められる多文化理解やインクルーシブ教育の実践力を育む貴重な機会となりました。
■今後に向けて
学部を超えた学生同士の協働は、お互いの学びを深める貴重な経験です。大西ゼミでは、今後もこうした取り組みを継続し、「学びがつながる大学」「地域に開かれた大学」を目指して活動を広げていきます。
▲左からアロカさん、大西先生、カウンターで準備をするのはシャーニカさん、トゥエンさん、スレーシさん
▲カウンターでフリーコーヒーの準備をする後輩にアドバイスをする4年生の先輩、下岡希空さん(右端)
▲今回は、心理学部心理学科の学生3名が参画しています。
左から、小井さん、鮎川さん、吉田さん